仕事をしていていると、一つや二つは「やりたくないこと」や「嫌なこと」は必ずあるものです。実際に仕事を辞めたいと思わなくても、積み重なってくると精神的にもつらくなりモチベーションが下がってしまうものですよね。
新しい仕事をする上で、デメリットも知っておかなければ入職後すぐに嫌になってしまい、継続して働くことはできません。今回は私が理学療法士として8年間、介護老人保健施設で働いてみて嫌だったことを5つ紹介したいと思います。
- リハビリ効果を実感しにくい
- 自分の専門以外の仕事もすることがある
- 認知症利用者の対応に苦労する
- 思ったより忙しい
- 職場の人間関係
実際に働いてみて嫌だと感じたことですが、私自身このようなことで仕事を辞めたいと感じたことはありません。
「絶対に耐えられない」と感じる方もおられるでしょう。逆に「思ったより働きやすいのでは?」と感じる方もおられると思います。人それぞれ許容範囲や得意分野も違うため、このようなデメリットも先に知っておくことも、今後の転職や就職を検討するにあたり重要な情報です。
この記事を読むと介護老人保健施設に就職を検討されている方の選択の手助けになります。私としては、介護老人保健施設で働く理学療法士が増えてより活性化することを願っています。
 | 【刻印対応】リットマン 聴診器 クラシック3【全30色】3M Littmann Classic III ステート【国内正規品】【あす楽対応】 価格:14980円~ |
リハビリ効果を実感しにくい
急性期や回復期で働いていると日毎に回復していく経過をみられるため、やりがいを感じやすい環境です。介護老人保健施設の利用者は、65歳以上の要介護状態で、在宅生活が困難になっている方達です。
身体面の特徴やリハビリ介入の制限など、効果を実感しにくいことが挙げられます。
加齢や発症からの経過が長い
担当する利用者は高齢の上、在宅での生活が困難となっておられる状態です。また、脳梗塞や変形性膝関関節症など多くの疾患を抱えている場合が多く、発症からの経過も長いためアライメントの崩れや拘縮の進行、慢性的な疼痛など問題点を抱えています。

入所時よりある程度今後の見立てをして、利用者の在宅生活復帰に向けて取り組んでいきますが大幅な身体機能の向上を見込めない利用者も多いのが現状です。また、入所中にコロナ罹患など体調を崩したり、転倒してけがをされ更に機能低下されるケースもあるため、モチベーションを保つことが難しいです。
身体機能や生活機能面全般の評価を行い、必要であれば必要な福祉用具や住宅改修の提案を行います。また、獲得困難な動作に関しては家族へ介助方法の指導や介護支援専門員と連携し介護サービス(訪問介護や訪問入浴など)を導入してもらうなど、必要なスキルは多義にわたるため病院勤務とは違った対応が必要です。
利用者の意欲が低い
リハビリに対しての意欲が低い利用者が多いです。徐々に身体機能が低下してこられているため、「こんな歳だからもうダメ」「どうせよくならない」とリハビリ自体拒否されるケースもあります。

また、認知機能が低下している利用者も多いため機能訓練的な運動がうまく導入できないケースもあるため病院で行っていたリハビリメニューでは対応できないことがあります。
利用者の今までの仕事歴や生活習慣、家族構成や趣味なども理解したうえで、今後どのような生活を送ってもらうことが良いのかを検討し、幅広い視野で対応していくことが必要です。また、利用者自身の「生きがい」なども含めて方向性を柔軟に考えていくことが大切です。

創作活動や編み物、買い物訓練など利用者ごとに受け入れやすい活動を取り入れた、個別のリハビリメニューを作成します。例えば創作活動にしても立ち座りや歩く機会を作るなど、身体機能向上に繋げるなどの工夫が必要です。
現実的にリハビリ介入時間が少ない
実際のリハビリ提供時間が圧倒的に少ないことも初めはびっくりするかもしれません。
急性期、回復期など病院では1日に最大180分リハビリの介入ができますが、介護老人保健施設では基本的には1週間に3日間で一回あたり20分間となっています。
短期集中リハビリテーション加算・認知症短期集中リハビリテーション加算(基準に該当していれば入所から3か月算定可能)などの加算を算定しても各プラス20分増える程度です。
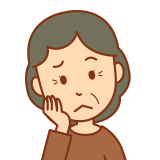
せっかくリハビリのために入所しているのに20分間ってあっという間ね。
機能向上には個別のリハビリ時間だけでは圧倒的に時間が足りません。
利用者に必要な時間の確保ができない分、施設内の生活現場でも介護職の見守りのもと、身体が動かせるように生活リハビリの設定が必要です。介護職への指導や連携などは必須の業務になってきます。

生活リハビリとは利用者が日常を生活する上で、着替えやトイレ動作などの活動内容をリハビリと捉え、自力でできるように介護職が効果的に支援する方法のことです。
 | 【即日出荷】ゴニオメーター(プラスチック角度計)角度計 計測 角度測定 計測器 アーテック 9724 価格:1448円 |
専門職以外の仕事をすることがある
理学療法士として働いてはいますが、必要があれば職域を超えて働く必要があります。
ADL評価
リハビリでは必須の業務ですが、利用者の身体機能を把握するため、ADL(日常生活活動)は全般で動作の評価が必要です。特にトイレ動作と食事動作は在宅ではかなり重要な動作となるため必ず確認します。
在宅でトイレの失敗があると同居家族の負担が大幅に増えます。便意尿意がなければ定時誘導やおむつ対応にするなどの対策も必要です。実際にトイレ介助することは非常に多いです。
食事は特に嚥下機能は窒息や誤嚥性肺炎などに繋がるため評価が必要です。入れ歯やトロミ材の使用の有無の確認や、食形態(刻み食、ペースト食など)の選定なども行います。私の施設では週に1日パートで言語聴覚士が働きに来ていますが、利用者も日々変化するため、理学療法士でもある程度の知識と対応できるスキルが必要です。

介護職の慢性的な不足
介護職の離職率は非常に高く、就職希望者も年々減っています。更に新しく有料老人ホームやデイサービスなどの施設が増えているため介護職の需要が高まっているため、介護施設の慢性的な介護職不足となっています。
介護職の不足によって利用者の不利益となる事態もしばしばみられるため、他のリハビリスタッフや看護士、事務員も必要時は介護の仕事をすることがあります。トイレ介助、おむつ交換、食事介助など介護職の仕事をすることは当然のようにあります。

介護職を経験することで普段の業務では見えてこなかった利用者の問題点を把握できたり、どのようにすれば業務効率が図れるかを一緒に感がるきっかけになったりと良い面もありますが、介護業務をすることが当たり前になってしまうと肝心のリハビリ業務が疎かになってしまうため、ある程度の線引きは必要だと思います。
最低限のリハビリスタッフ
リハビリ職の賃金は比較的高めに設定されている施設は多いと思います。施設運営のため、必要最低限のリハビリ職員で仕事を回さざるおえない状況があります。
人員配置としては入所者100名に対してリハビリ職員1名以上となっていますが、超特化型の介護老人保健施設では充実したリハビリとして入所者に1週間3回個別リハビリの介入が必要となってきます。

超強化型の介護老人保健施設とは、厚生労働省が定める在宅復帰・在宅支援機能といった要件を満たした施設の事です。
短期集中リハビリテーション加算や認知症短期集中リハビリテーション加算、入退所訪問指導など必要業務を考えると最低4~5名はリハビリスタッフが必要になります。
私が働いている職場では利用者定員100名です。施設担当のリハビリ職員としては理学療法士2名(パート1名)、作業療法士4名(パート1名)、言語聴覚士1名(パート1名)が勤務しています。パート勤務の職員は就業時間も短いためギリギリの人員で働いています。
| 正職員 | パート職員 | |
| 理学療法士 | 1名 | 1名 |
| 作業療法士 | 3名 | 1名 |
| 言語聴覚士 | 0名 | 1名 |
理学療法士であっても嚥下訓練や認知機能訓練、作業活動なども担うことは当たり前です。ある程度一人でも利用者の生活全般を管理していかなければなりません。それぞれの職域というよりも一人のリハビリ職員として対応する必要があります。
得手不得手はあるため適宜足りない知識などは相談することもありますが、自分の職域以外の勉強も必須になります。
認知症利用者の対応
高齢者の数が増えると同時に認知機能低下により在宅生活が困難となるケースが増えています。
私の施設では入所者数100名の内半数の50名は認知症棟を利用されています。それ以外の利用者にも認知症の方がおられるため、原因や対応方法を理解したうえで働く必要があります。
中核症状(記銘力の低下)だけであれば対応方法は難しくはないのですが、周辺症状に対応が困ることが多々みられます。

- 被害妄想(物とられ妄想、毒を飲まされているなど)
- 暴力・暴言(職員や他利用者)
- 介護拒否(食事・トイレ・入浴など)
- せん妄(急に興奮したりつじつまの合わないことを言うなど)
- 異食(食べ物以外のものを食べる)
- 収集癖(ペーパータオルや色鉛筆など)
- 弄便(ろうべん:便をいじる行為)
- 徘徊(施設からいなくなることもあり)
上記以外にも人によってそれぞれ違った症状があります。誤嚥や転倒、暴力など利用者や職員の怪我や命にかかわることもあるため適宜対応方法を検討します。
対応方法の基本は
- 信頼関係を築く
- せかさず利用者のペースに合わせる
- 否定しない
- 優しく丁寧に接する
などの対応となりますが、周辺症状や利用者毎に対応不法も違ってくるので介護士、看護師、相談員などとも常に話し合いをしながら対応方法を検討していきます。


私の施設では精神科医も定期で診察に来てもらっているため、関り方や必要に応じてお薬も処方してもらうことがあります。
思ったより忙しい
施設によっても違いはあると思いますが、私の働いている施設は超特化型の介護老人保健施設のため要件を満たす必要があります。
一日のリハビリ介入は平均20単位程度になります。それ以外にもケース会議や入退所訪問指導、介護指導、カルテ記載、計画書の作成(厚生労働省への情報提供)、環境調整など必要な業務があります。

正直、一日の中で必要な業務量は多いため、計画を立て優先順位を決めて働く工夫が必要です。リハビリ加入ができていないと超強化型の算定要件にもかかわってきます。施設の収入が大幅下がってしまう事態になるため注意が必要です。
ゆっくりと働きたいのであれば基本型の介護老健施設に就職したほうが良いかもしれません。しかし忙しい分スキルアップややりがい、収入面などメリットも多いですよ。
人間関係
これは介護老人保健施設だけの問題ではなくリハビリ職全般に言えますが、関わりにくい上司がいました。考え方ややり方を強要してきたり、長時間叱責するなど一緒に働くにはとてもストレスになるいわゆるパワハラ気質の職員です。

職場のパワーハラスメントとは、
- 職場において行われる優越的な関係を背景とした言動
- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
- 労働者の就業環境が害されるもの
であり、1から3までの3つの要素を全て満たすものをいいます。
なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワーハラスメントには該当しません。
私の場合は再度転職も検討しましたが、ダメもとで他のリハビリ職員と団結し、証拠集め(時間や内容、録音など)や施設長への相談などを行った結果、一緒に働かなくてもよい環境にパワハラ上司を移動してもらうことができました。現在はその上司は退職したため、穏やかな職場環境になっていますが本当につらい状態でした。

離職の一番の原因となると考えているため、皆様もパワハラを受けた際の対応方法を考えておくとよいと思います。
まとめ
今回は介護老人保健施設で働いてみて嫌だったことを解説しました。
病院勤務に比べるとリハビリ効果を実感しにくいこと、理学療法士として勤務しているが作業療法士・言語聴覚士・介護職などの仕事をすることがあること、認知症利用者の数が多く、特に周辺症状の対応が思った以上に大変なこと、ゆっくりと働けると思いきや業務に追われること、パワハラ気質の職員がいたことが私にとっては嫌なことでした。
自分なりにどうしようか考え対応できているため、退職したいとまでは感じていません。
(パワハラ上司の件は少し退職を考えましたが…)
働いている以上は何かしらの嫌なことはあると思います。そのような時でもどのようにすればよいのか模索し対策していけばそれなりに楽しく働くことができると思いますよ。
今回の解説で介護老人保健施設の興味をもった方は是非、転職や就職の際に検討いただければ幸いです。




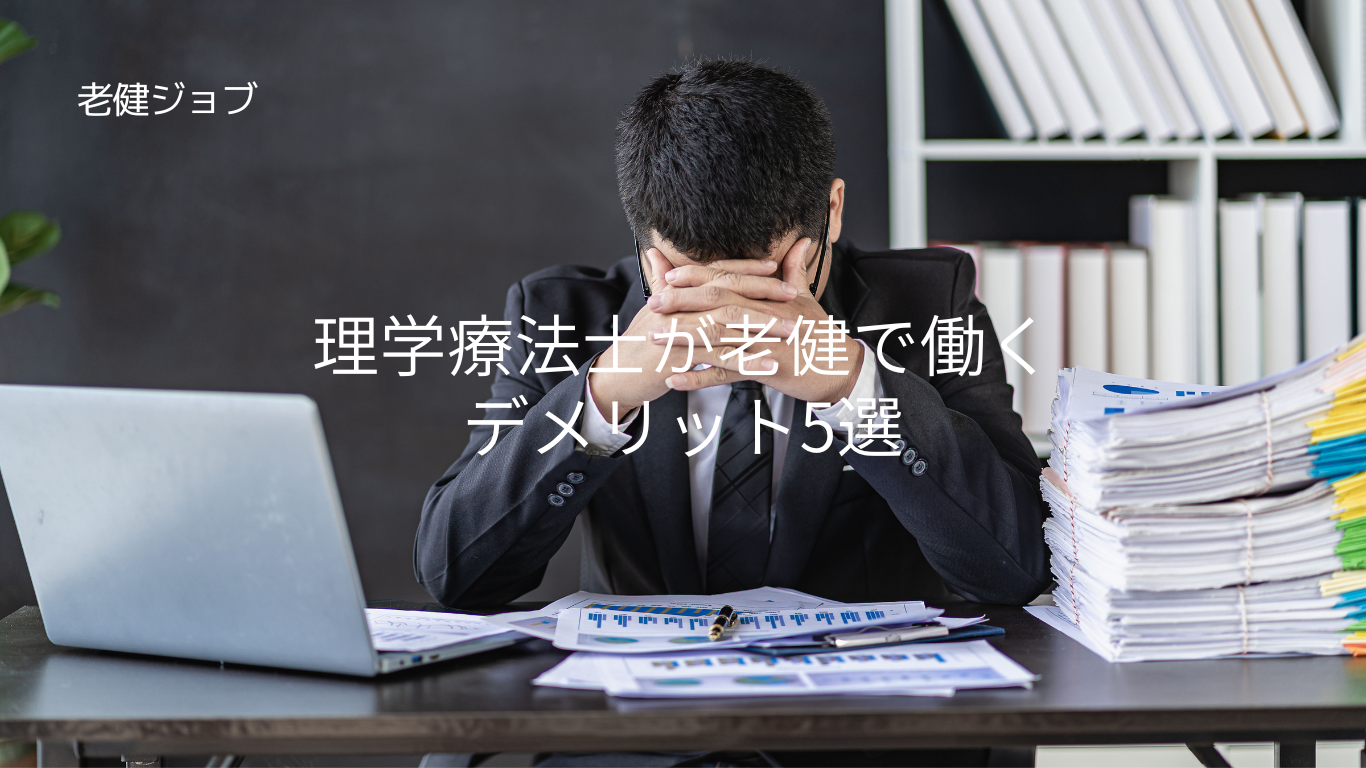


コメント