理学療法士は養成校を卒業してから初めの就職先は病院、クリニックなど医療機関が8~9割といわれています。
現在は高齢者の増加や職域の広がりから、介護業界で働く理学療法士の割合も増えてきています。
実際私も病院で7年間勤務した後、介護老人保健施設(以下老健)に転職した経緯があります。介護施設は介護保険を使った運営をしているため、転職当時は戸惑うことも多い状態でした。
ちなみに特別養護老人ホーム(以下特養)には生活機能連携加算という施設間の連携業務があり、月に数回訪問しリハビリや介護に関する指導や計画書の作成などの業務を担っています。
特養は別名で介護老人福祉施設と呼ぶこともあります。介護老人保健施設と介護老人福祉施設は名称がかなり似ているので混同しやすいですね。
今回は同じ介護施設である、老健と特養についてどのような違いがあるのか、働き方の違いなどを詳しく解説していこうと思います。
実際どちらがいいかは人により違うと思いますが、内容を知っておくことで安心して転職することができると思います。
老健と特養の基本的な違い
基本的には老健、特養共に生活施設であるため、食事や入浴といった基本的な生活の場であることには変わりありません。しかし、生活の目的が大きく違います。
| 介護老人保健施設 | 特別養護老人ホーム | |
| 概要 | 要介護者が在宅復帰を目指すリハビリ施設(病院と在宅の中間施設) | 常時介護を必要とし、在宅での生活が困難な高齢者に対して、生活全般の介護を提供する施設(終の棲家) |
| 入所条件 | 要介護1以上 | 要介護3以上 |
| 入居期間 | 原則3か月終身 | 終身 |
| 費用の目安 | 9~20万円(負担割合1割) 入居一時金不要 | 8~13万円(負担割合1割) 入居一時金不要 |
| 職員配置基準 | 医師: 100:1 看護師 100:3 介護職 3:1 リハビリ職員 100:1 支援相談員 100:1 介護支援専門員 100:1 栄養士 100:1 | 医師 必要数 看護師・介護職 3:1 機能訓練指導員 100:1 生活相談員 100:1 介護支援専門員 100:1 栄養士 100:1 |
介護老人保健施設
介護を必要とする高齢者が日常生活に戻るための介護やリハビリテーションを受けられる施設です。退院後に自宅へ戻ることが難しい身体状態のときなどに利用され、自宅生活への復帰を目的に機能訓練に取り組みます。

在宅復帰を目指す施設のため、入居期間にある程度の決まりがあります。入居者の入れ替わりが激しい施設です。
介護老人保健施設とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設。【介護保険法第8条第28項】
入所条件は要介護1~5の在宅復帰を希望されている利用者です。
入所期間は原則3ヶ月ですが、機能向上が見込めない場合や介護者の有無、ターミナルケアを受けておられる方など当てはまらない方もおられます。
入所中の費用に関しては介護度や負担割合、加算の算定などによって大きく変動します。目安としては1割負担で9~20万円/月となっています。
職員の配置基準はほとんど変わりありません。リハビリ職の配置基準は利用者数100名に対して1人となっています。リハビリ職員とは理学療法士、作業療法士、言語聴覚士が必要です。

実際には算定要件により個別で1回20分以上、週3回のリハビリ介入が必要であったり、リハビリに関する加算など算定していくと100名に対して最低でも5~6人のリハビリ職員が必要です。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)
常時介護を必要とし、自宅での介護が困難な高齢者のための福祉施設です。
入浴・排泄などの介護サービスや機能訓練、食事の提供、生活支援などを受け、生活の質を保ちながら長期的に暮らすことができます。

65歳以上の者であって、身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることが困難なものを入所させ、養護することを目的とする施設【老人福祉法第20条の5】
入所条件は要介護3~5で在宅生活が困難になっておられる方です。
体調の変化により専門的な治療が必要で入所困難となる可能性はありますが、基本的には長期の利用を前提としています。よく特養は「終の棲家」と言われます。
入所中の費用に関しては介護度や負担割合によって変動します。目安としては1割負担で8~13万円/月となっています。
職員配置基準は老健とほとんど変わりませんが、リハビリの概念が老健とは違います。機能訓練指導員が利用者100名に対して1人となっています。
機能訓練指導員とは、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、柔道整復師、あんまマッサージ師、はり師となっており、リハビリ職が必ず在籍する必要はありません。

基本的に機能訓練指導員の数は最低限(一人職場)の施設が多いです。施設の目標としては機能維持を図ることや、生活の質を上げることが目的であるため頻回な介入は難しいです。長期間ゆっくりと関係性を築いていくことが得意であれば働きやすいと思います。
実際のリハビリ業務について
老健のリハビリ業務
老健では基本3か月で在宅復帰を想定しているため、機能向上に向けての取り組みが必須となってきます。また、在宅復帰に伴い入退所前後に在宅訪問も行い、在宅環境を理解したうえでのリハビリ提供を行います。
また、入退所が頻回にあるため担当者会議や計画書の作成など必要業務が多いため実際の業務は多忙であることが多いです。
高齢者で急性期、回復期の病院とは違い機能向上については難しい面もありますが、環境調整や福祉用具の使用など評価することも多くやりがいはある仕事です。
特養のリハビリ業務
特養では終身利用を想定しているため、ご利用者の機能維持や楽しみをもって生活することなどが重要になってきます。
3か月に1度の計画書作成など業務はあります。頻回な介入は難しいですが、入退所は少ないためゆっくりと時間をかけて長期的な介入をすることができます。
基本的には少人数(一人職場が多い)での関りとなるためリハ職間での相談はできません。看護士、介護職と連携していく必要があるため老健よりも更にコミュニケーション能力が高いことが望まれます。
施設の中の困りごとなども相談されることも多いため老健同様にやりがいはあると思います。
リハビリ介入についての収益は老健が高い
老健と特養ではリハビリに関する収益が違います。両方の施設ともに加算が細かく分かれているため、リハビリに関する収益についてまとめてみました。
細かな加算に関しても老健のほうが圧倒的に単位数が高いことがよく分かると思います。
収益に関しては圧倒的に老健に軍配が上がりますが、その分老健はリハビリ職員や医師、看護師などの必要人員が増えるため人件費が高くなる傾向があります。人員が多い分必要加算をとるなど仕事量も増えるといえます。
老健と特養のリハビリ介入によっての収益の違い
老健のリハビリに関する単位数
老健ではリハビリ介入することが前提で入所単位数に反映されているため収益は高くなります。介護度によって単位数は違い介護度が重いほど単位数は増えていきます。下の表は多床室で在宅強化型の単位数です。
介護保険施設サービス費(Ⅰ)(ⅳ)(多床室)(在宅強化型)
| 介護度 | 一日当たりの単位数 |
| 要介護1 | 871単位 |
| 要介護2 | 947単位 |
| 要介護3 | 1014単位 |
| 要介護4 | 1072単位 |
| 要介護5 | 1125単位 |
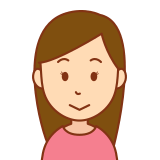
老健・特養共にの居室には「多床室」「従来型個室」「ユニット型個室」「ユニット型個室的多床室」と4つのタイプがあり、それぞれ単位数が分かれています。

老健は在宅復帰率などに応じて「超強化型」「在宅強化型」「加算型」「基本型」「その他型」の5種類の区分に分類されています。詳細は別記事で説明予定です。
短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) 258単位/1日
入所した日から3カ月間。20分以上のリハビリテーションの提供。週3日以上実施。
入所時及び月1回以上ADL評価の実施と科学的介護情報システム(以下LIFE)提出を行うこと。

科学的介護情報システム「LIFE」とは、利用者の情報や介護サービス提供に関する内容のデータを厚生労働省へ提出することと、データ解析によるフィードバックの活用によって、科学的に裏付けられた介護の実現を目指しサービスの質の向上を図る取り組みをするためのシステムです。
短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) 200単位/1日
入所した日から3カ月間。20分以上のリハビリテーションの提供。週3日以上実施。
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅰ) 240単位/日
認知症であると医師が判断した者(MMSE、HDS-Rが5~25点)。週3回が限度。
リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者。
居宅を訪問し、把握した生活環境を踏まえたリハビリテーション計画を作成していること。
認知症短期集中リハビリテーション加算(Ⅱ) 120単位/1日
認知症であると医師が判断した者(MMSE、HDS-Rが5~25点)。週3回が限度。
リハビリテーションによって生活機能の改善が見込まれると判断された者。
特養のリハビリに関する単位数
特養では積極的なリハビリ介入することが前提ではありません。そのため老健よりも全体的に単位数が少ないことが分かります。下の表は多床室の単位数です。
介護福祉サービス費(Ⅱ)(多床室)
| 介護度 | 一日当たりの単位数 |
| 要介護1 | 589単位 |
| 要介護2 | 659単位 |
| 要介護3 | 732単位 |
| 要介護4 | 802単位 |
| 要介護5 | 871単位 |
個別機能訓練加算(Ⅰ) 12単位/1日
機能訓練指導員が個別機能訓練計画に基づき、計画的に個別機能訓練を実施。
多職種が共同して利用者毎にその目標、実施方法を内容とする個別機能訓練計画書を評価に基づき3か月に1回作成する。
個別機能訓練加算(Ⅱ) 20単位/1月
個別機能訓練加算(Ⅰ)を算定していること。
利用者毎の個別機能訓練計画書の内容をLIFEに提出する。
個別機能訓練加算(Ⅲ) 20単位/1月
個別機能訓練加算(Ⅱ)を算定していること。
口腔機能訓練加算(Ⅱ)または、栄養マネジメント強化加算を算定していること。
機能訓練指導員が個別機能訓練計画書や口腔の健康状態、栄養状態に関する情報を相互に共有していること。
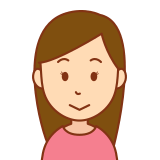
口腔機能訓練加算(Ⅱ)とは口腔機能の改善及び維持、介護度の悪化防止や改善を目的とした加算です。160単位(2回/月まで)
栄養マネジメント強化加算とは栄養ケア・マネジメントの取り組みを一層強化することを目的とした加算です。11単位/1日

介護保険サービスは基本点数プラス加算や減算などたくさん存在しています。リハビリの介入以外でも何かしらの取り組みにより収益の増加が見込め、利用者に還元できる可能性があります。施設長にも適宜連携を図りながら算定していくことが必要です。収入アップに繋がると思います。
収入の違い
老健と特養どちらで働いた方が収入は高いのでしょうか。
厚生労働省「令和3年度介護従事者処遇状況等調査結果の概要」では介護施設全般の平均月収しか調べることができませんでした。求人案内などで調べた結果、特養のほうが若干収入は多いようです。
| 職種 | 平均月収 |
| 看護職 | 369.760円 |
| 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・機能訓練指導員 | 351.230円 |
| 介護職 | 315.640円 |
| 介護支援専門員 | 332.640円 |
原因として、昔は求人を出してもリハビリ職員が集まらなかったという話をよく聞きます。何とか職員を集めるために収入を高くして求人を出していた経緯があるようです。最近では理学療法士の数が増えてきたため希望者も増えてきており、各介護施設ともに収入を減らす方向に動いているようです。そのため早めの転職活動が良いと思います。
| 職種 | 平均月収 |
| 介護施設の理学療法士 | 351.230円 |
| 全体(病院も含む)の理学療法士 | 296.000円 |
ちなみに理学療法士の職域全般でみると、介護施設の理学療法士の収入は少し高いことが分かります。
まとめ
老健は在宅復帰を目指す利用者がリハビリをすることを目的とした施設です。リハビリに関する加算も多く施設の利益は上がりやすく目標を立てて働くことができます。リハビリ職員は5~10人程度で比較的多く相談しながら進めていくことができる職場です。
特養は在宅生活が困難となった方が長期の利用を前提とした施設です。リハビリに関する加算は少なく長期にゆっくりと関わっていくことができます。リハビリの職員は一人の事が多く施設職員とのコミュニケーションは必須です。
収入に関しては病院に比べると介護施設の理学療法士の収入は高いといえます。収入面でより高収入の職場に行きたい方は試してみてもよいのではないでしょうか。
老健と特養はどちらがいいとは一概には言えませんが、私は老健で働いており在宅復帰に向けた関りがとても自分の性格に合っていると感じています。特養に関しても一人職場が多いですが、ある程度病院などで経験があり、コミュニケーション能力に自信のある方であればお勧めの職場といえます。
上記でも述べていますが、理学療法士の増加に伴い収入が抑えられてきています。転職を考えている方は早めに動いた方がよいでしょう。まずは転職サイトに申し込んで、どのような求人があるかを調べておくとより動きやすくなると思います。いつ好条件の求人が出るかは分かりませんからね。




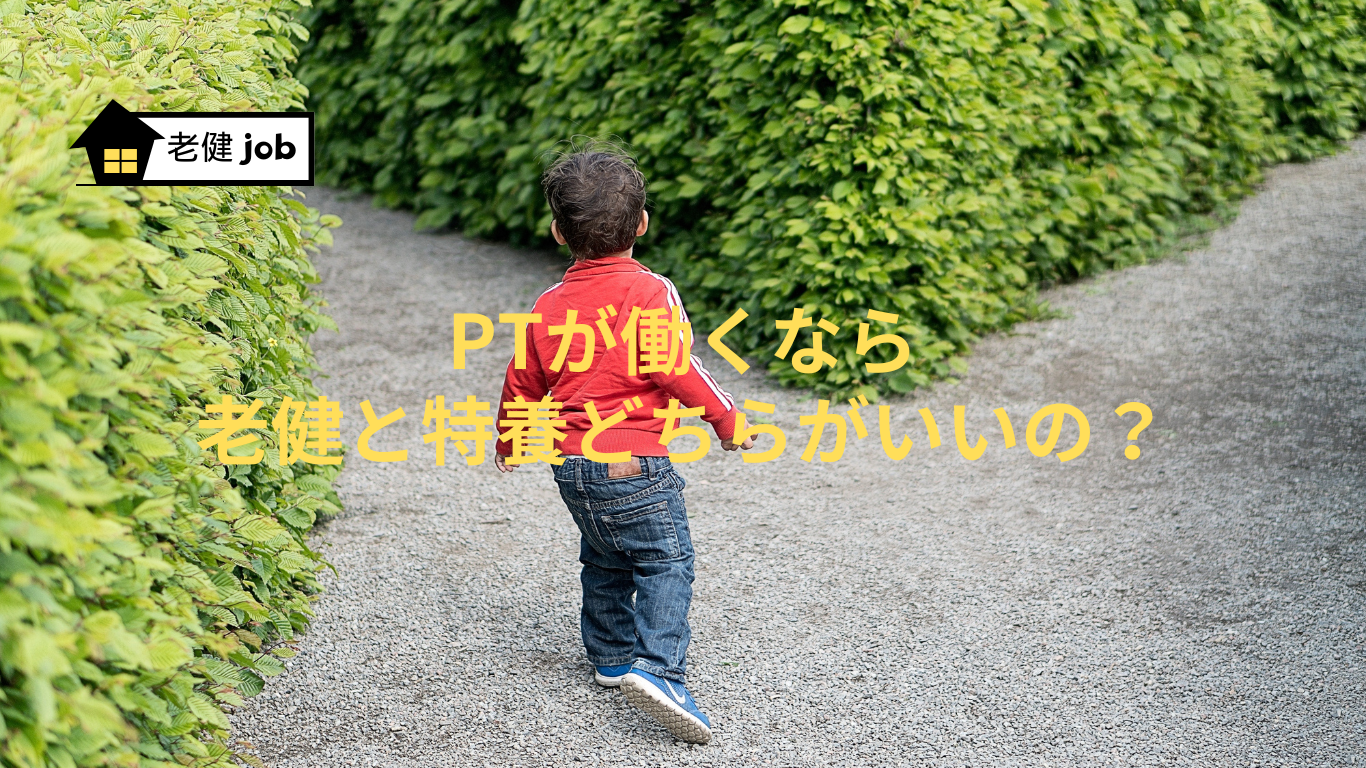

コメント